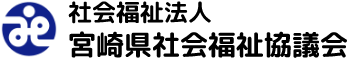地域福祉コーディネーター
地域福祉コーディネーターとは
地域福祉コーディネーターは、様々な福祉施策やサービス、または福祉活動を行っているボランティア、NPO等の情報など、地域の福祉課題を解決するために利用できる多くの手段・情報に精通した人材のことで、平成19年度より養成を開始しました。
これまで、行政職員をはじめ、社会福祉協議会職員、社会福祉施設職員、NPO法人職員等、761名の方々が養成研修を修了し、それぞれ施設や関係機関等に所属しながら実践活動を展開しています。
地域福祉コーディネーターは、基盤となる所属組織、専門性がある中に、地域福祉の理念や手法を加え、様々な関係機関・団体等と連携・協働し、地域の課題解決に向けてリーダーシップを発揮する「地域福祉推進のキーパーソン」としての役割を担っています。
地域福祉コーディネーターの役割(イメージ図)
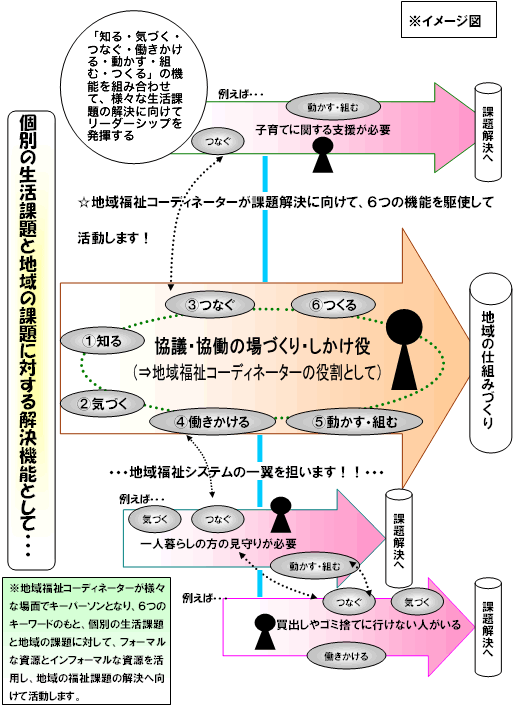
役割1:知る
ポイント(1)地域の現状を知りましょう
- 地域の困りごとや自慢できることなど、短所も長所も知りましょう。
- 地域の短所も活用次第では大きなきっかけや成果へ結びつくこともあります。
ポイント(2)地域にある様々な社会資源を知りましょう
- 地域にある様々な社会資源(行政関係機関、医療福祉関係機関、ボランティア、任意団体、企業商店街、自治組織等)を把握しましょう。人材・施設など分野に分けて資源マップづくりをしてみるのも効果的です。
こころがけ:まずは地域を知ることが大事!!(学びの場・出会いの場)
- 地域の生活課題(歴史・文化・地勢なども含む)を様々な「集まり」(地域活動・イベント・会議、交流会など)に参加しながら把握しましょう。
- 違いがあって当たり前!
- 雑談・懇談の場からも地域を把握しましょう。
- となり近所のかたやイベント等に参加している人とも知り合いになりましょう。
- 地域福祉活動(サロン活動・座談会・自治公民館活動)の現場に参加・参画しながら、活動者・参加者と知り合いになりましょう。現場活動への参加は仲間づくりへの一歩。
- 歴史・文化・土地柄を知るために文献等から情報を入手しましょう。
- 「てげてげ...」も心に余裕のある証し!
役割2:気づく
ポイント:地域の課題(ニーズ)をキャッチするアンテナをはろう
- 今、地域で何が課題なのか、地域住民がどのようなことに関心を持っているか、おもしろそうなことを言っている人は誰か、どこに行けば社会資源にあたれるか、つねにアンテナを張って情報のストックを蓄えましょう。
- 苦手な人の輪に入るには必要以上のエネルギーがいりますが、そのことで、成果や効果はそれ以上の結果を得ることがあります。
こころがけ:常にアンテナを張ることが大事!!
- 豆知識は日頃の井戸端会議や広報チラシから!⇒福祉制度・サービス、近隣領域(保健・医療・福祉など)の制度やサービスについての知識を持ちましょう。
- 地球はまーるい!人類みな平等!⇒関係領域(環境・教育・芸術、外国人など)の状況や課題・動静などについての関心と知識を持ちましょう。
- 地域への参加はまずできることから...まずはあいさつ!⇒地域の人材・組織・施設等などとの日頃からのおつきあい(あいさつからイベント・事業等への参加など)を欠かさないようにしましょう。
- 地域には元気な人もいるけど、「いろんな事を言いたいことがあるけど、なかなか言えない人」がいるかもしれません。
役割3:つなぐ
ポイント:人と人をつないでいこう!
- 求められているサービスを提供している機関、組織につなげることも大切ですが、真の課題解決になるとは限りません。だから生活ニーズに合っているか、自分らしい暮らしが送れるか、などを適切に判断していくことが必要です。
- 柔軟な発想と対応は、コミュニケーション力を高め、お互い助けられたり、助けたりの効果につながります。
こころがけ:助け上手、助けられ上手になろう!!
- 様々な生活ニーズに応えることのできる地域の社会資源(マンパワーも含めて)とのネットワークづくりが必要です。そのためには、まず役割1の「知る役割」が必要なことかもしれません。思い浮かんだ社会資源には必ず役割がある!
- 地域の中の生活ニーズに対して共通理解(共有)する場が必要かもしれません。まずは、地域の様々なことについてみんなが話し合える環境をつくってみることからはじめてみましょうか?隣りの人と伝え合えば2つのアイデアに...!そして仲間に...
- 自分一人だけでは限界があります。様々な人とつながり、連携、協働することが大事です。そのために「助け上手、助けられ上手」になりましょう。助けられた事は、助ける時にそれ以上のお土産に!
役割4:働きかける
ポイント:地域の課題を地域住民みんなで考えるように働きかけよう
- 生活ニーズはその個別のケースだけの課題なのでしょうか?その人のことはその人だけのことでしょうか?地域みんなの課題として捉え、様々な人や機関への働きかけが必要かもしれません。
- 1人の課題解決は、住民の課題解決とまちづくりのきっかけになるかもしれません。
こころがけ:みんなで考える場づくりを!!
- みんなで考える場をつくってみませんか?(⇒共有・協議の場の設定) ⇒地域住民の生活課題などを把握できたならば、次はその課題を地域住民や関係機関、職員間などの関係者に伝え、問題意識をもってもらう段階に入ります。 地域の福祉課題の中にはプライバシーに関わることもあり、伝え方の工夫や関係者の了解が必要であり、正式な手順を必要とすることもあります。また課題を課題としてまるで認識していない場合もあります。課題解決の必要性を知らせるといっても様々なことを考慮に入れ、その時々にあった方法(働きかけ)を用いる必要があります。
- 根回しや飲みニケーションという「日本人的コミュニティワークの手法」を使った働きかけも時には必要になってくるかもしれません。
役割5:動かす・組む
ポイント:共通理解を図り、動かし・組んでいくことが大事です
- 地域住民とともに地域を基盤にした支援を展開していきましょう。「点」から「線」へ、そして「面」へひろげていくことです。
- できることを1つずつ実践していくことで、1人の一歩が百人の一歩につながることもあります。
こころがけ:心が動けば、体が動く!!
- 相手を動かすには、まず自分が動く!(⇒お互いの違いを認めた上で...)
- 動かす・組む対象者に対しての自分自身の信頼度を見極めましょう。
- 動かす・組む対象者において、時には発言力がある人・団体を把握することが大事かもしれません。
- 話し合いなどでどの意見をどのように取り入れたかを明確にしましょう。話し合いへの参加者自身が発言したことが無駄になっていないと認識できると、今後の話し合いでも前向きに発言していこうという気持ちが起きます。また意見が反映されたから、一緒に組んでみましょうという気持ちになることも...
- 説得ある資料作成能力と話術を身につけることも大事かもしれません。
役割6:つくる
ポイント:いろんな場をつくりだす「しかけ役」に
- 現在、新しい福祉課題が増大している状況にありますから、その様々な課題を解決していくためには、いろんな場づくりが必要です。場合によっては、地域を揺り動かすような問題提起と行動を積極的に起こし、「地域のしくみをつくりなおす」ことが必要になるかもしれません。
- 協議の場を設けると、参加者のアイデアや想いがきっかけになり、アイデアや新しい支えあいのきっかけづくりにつながることもあります。
こころがけ:「住民とともに」を基本に、側面的に支援!!(協働の場)
- 様々な場づくりこそが、「つくりだす」役割かもしれません。
- 把握した課題に対する解決策として、新たなサービス、しくみをおこす(あるいは改善する)必要がある場合は、[1]既存組織への働きかけ、[2]新たなサービス提供者の組織化、[3]自らのサービス開発のいずれかがあります。既存の社会資源の最大限の活用や、住民の主体的な活動をおこすべく様々な働きかけが必要になってきます。 このようなしかけのテクニックは具体的なノウハウが蓄積されていません。しかし前述したとおり、「心を動かす」しかけが新たなサービスの創出へつながるかもしれません。
地域福祉コーディネーター実践モデル事業(過去に取り組んだ事例)
地域福祉コーディネーターの活動支援とその普及を図るため、本会ではモデル事業を実施してきました。 その取り組みについて以下にご紹介します。
- 【令和元年度】社会福祉法人日向市社会福祉協議会東郷支所(日向市)
- 【令和元年度】一般社団法人福八(都城市)
- 【令和元年度】社会福祉法人愛鍼福祉会 宮崎南デイサービスセンター(宮崎市)
- 【令和元年度】社会福祉法人まりあ(都城市)
- 【令和元年度】社会福祉法人敬愛会 のじり地域包括支援センター(小林市)
- 【令和元年度】子育て応援ユニット「チーム宮崎県」(宮崎市)
- 【平成30年度】特定非営利活動法人日向市手をつなぐ育成会「スマイルホーム360」(日向市)
- 【平成30年度】一般社団法人福八(都城市)
- 【平成29年度】特定非営利活動法人ドロップインセンター(宮崎市)
- 【平成29年度】社会福祉法人諸塚村社会福祉協議会 特別養護老人ホームもろつかせせらぎの里(諸塚村)
- 【平成28年度】特定非営利活動法人ふぁむ・ふぁーむ(木城町)
- 【平成28年度】社会福祉法人まりあ(都城市)
- 【平成28年度】住吉地区社会福祉協議会 住吉ボランティアセンター「つなぎ」(宮崎市)